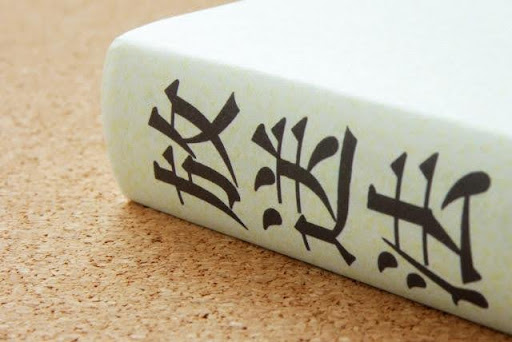少し前に「コンプライアンスが厳しすぎる」というのをテーマにしたドラマが注目されたように、今は放送業界を取り巻く規制は何かと話題にあがります。
今回は、テレビ業界を目指す人なら知っておきたい『放送法』についてまとめていきます!
放送法ってなに?
放送法は敗戦後、戦争が終わった後の1950年にできた法律です。実は放送法ができたのは、かつての戦争がきっかけでした。当時はテレビがなく、主な情報源はラジオと新聞でした。戦前から政府に管理されていたラジオが戦争に協力する内容の放送をしてきたことを反省して、放送の独立性を守るために、放送法ができました。
新しい憲法に沿った“民主的な放送”が行われるようにするための法律です。政府や政治が番組の内容に干渉しないようにするのが放送法の趣旨になります。
一方で、日本国憲法は「表現の自由」を明確に定めました。つまり、大原則としては、各放送局は自由に番組を作ってよく、また、健全な民主主義を守るためにも、そうあるべきとされています。

放送法ってどんなことが定められてるの?
第1条では、法律の目的として「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」と掲げています。
つまり、放送がどんな勢力にもかたよらない「不偏不党」や、権力に操られず独立して運営する「自律の保障」に基づいて、表現の自由を確保するように定められています。
第3条では、放送する番組について「何人からも干渉され、又(また)は規律されることがない」と、番組編集は自由だと明記があります。
次の第4条では、番組編集について4つの基本方針を定めています。
・公安及び善良な風俗を害しない
・政治的に公平である
・報道は事実をまげないでする
・意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする
放送禁止用語は実は法律で決まっていないって本当?
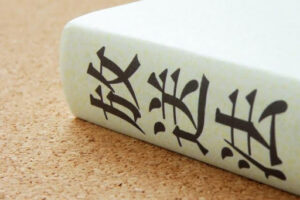
テレビでは不特定多数の人が視聴しているため、その放送内容や出演者の発言において重大な責任がありますよね。そのため、テレビ局側では放送で使う言葉や表現方法に気をつけており、「放送禁止用語」が定められています。
テレビ局は「放送禁止用語」を設けることで、人権を守ったり、視聴者が不快にならないように努めているのです。
では、放送法で「放送禁止用語」が決まっていると思いきや実はそうではないのです。放送禁止用語は放送業界で統一されたリストなどがあるわけではありません。テレビ各局や番組担当者がその都度、放送倫理に照らして、問題がある場合には自粛や自主規制をするために「ピー」という音をかぶせたり、裸の一部にモザイクや画像がかぶさり隠しています。つまり、「放送禁止用語」や「放送基準」は各々の放送局の判断にまかされているというのが実態です。
再放送では放送できないものもある
例えば、規制が比較的緩かった過去の映像を再放送するときはどうなるのでしょうか。
過去に比べて現在は、より人権を尊重する時代、差別を禁止する時代となってきました。そのため、どうしても、過去には放送できていた言葉や映像などが現在では放送できないということもでてきてしまいます。そのため、過去のアーカイブ映像や昔のアニメなどにおいては放送上でモザイクがかけられたり音声が途切れたりすることがあるのです。
その他にも、例えば生放送の番組ではどうなるのでしょうか。
もちろん間違いや周知されていない言葉によって放送コードに触れてしまうこともあります。その場合には番組の司会者などが、後に発言についてのお詫びをするなどして対応しています。
放送禁止用語がテレビ局によってバラバラなのはなぜ?
このように、テレビ局や番組によって放送禁止用語が規定されていないのは、「表現・言論の自由」が尊重されているからです。ただ、欧米では放送禁止用語リストや規則条項などを設けている国もあるといいます。
過去の知見や失敗をまとめた「民放連 放送基準」とは?
とはいえ、全くバラバラの動きをしているわけではありません。
ほとんどの放送局が番組基準として準用している「民放連 放送基準」というものがあります。これは、放送局の諸先輩方の貴重な知見や失敗を集めたものです。また、それぞれの条文の理解を深めてもらうため、「民放連 放送基準解説書」という冊子も用意されており、会員各社の手元に届いています。
「民放連 放送基準」は2023年に”令和の大改正”と呼ばれるほどの条文・解説に見直しが行われました。それだけ世の中の価値観も放送を取り巻く環境も大きくかわった時代を私たちは生きています。
テレビ局の考査部が放送基準を守っている
冒頭では「テレビの表現は自由」と説明しましたが、正確には少し違うともいえます。テレビ局には、放送基準や各種法令に照らし合わせ放送前の番組を確認する「考査部」(局によって部の名称は異なります。)があります。考査部には、制作局・事業局・営業局などから放送前の様々な番組やCMが持ち込まれ、そこで、「この番組を視聴者が見た時にどう感じるか」という視点で確認していきます。

放送禁止用語の定義とは?
「放送禁止用語」かどうか判断するときに大事になってくるのが、≪誰が使うか、どう使うか、どこで使うか≫です。
例えば、以下の言葉も、実は放送事業では放送注意用語に該当しています。
「八百屋」「ペンキ屋」「運ちゃん」
この3つの放送適正用語としては
「八百屋」⇒「青果店」
「ペンキ屋」⇒「塗装業」
「運ちゃん」⇒「運転手」
とされています。
ただし、これらの言葉も本人が使うこと自体は問題がないとされています。これは「用語に対して自分が関係者として責任を担える」と考えられているからです。「あれもダメこれもダメ」というわけではなく、「人を傷つけるのはやめよう」という、ごくごく当たり前の事実をしっかり考えていこう、ということですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。何かと話題になる「放送禁止用語」についてご理解いただけましたでしょうか。コンプラでガチガチに固められた時代ともいえる今、「そのせいでテレビがつまらない」という意見もありますが、メディアの中でもとりわけ大きな影響力を持つテレビは、用語の使用に敏感になるのは致し方ない側面もあります。安心して番組を各家庭に届けるためにも、「放送法」や「放送禁止用語」などをしっかり理解して、番組作りを行っていく必要があります。